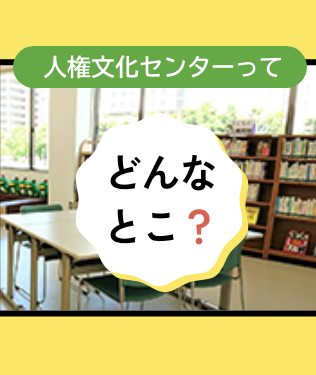じんけん放話3「誰もが『権利の主体者』である!」
先日、公民館主催の高齢者学級で「高齢者の人権」について講演を行いました。「高齢者に関わる人権問題を包括的にお話してほしい」との依頼です。
まずは超高齢社会の現実をグラフで示します。日本は高齢化率(人口に占める65歳以上の人の割合)が30%に迫っており、世界でも類を見ない超高齢社会であること、2025年には団塊の世代全員が75歳を迎え医療や介護の面で財政が逼迫し、かつ介護の担い手不足が深刻なこと、高齢者夫婦のみの家庭や一人暮らしが増えていることなど、日本の厳しい現状を目の当たりにして、会場からはため息が漏れ聞こえます。
次に、「高齢者虐待」「貧困の問題」「孤独」「認知症への偏見」など、高齢者が直面するそれぞれの問題ごとに現状を示すとともに、施策や取り組み、事例などを紹介していきます。一般に生活弱者と言われる高齢者を「保護の対象者」として捉え、その人権を守っていくためにはどのようにしていくかというお話です。参加者は頷きながらも、どこか冴えない顔をしてお話を聞いていました。
さらに人権の話を広げていきます。
「高齢者の国連原則」に則り、「生きがい」や「ボランティア活動」「当事者会議への参加」等へ話が及びます。これらは高齢者自身が自らの意思で判断し行動できることを保証するもので、「自己実現の原則」「参加の原則」などと呼ばれています。言わば、高齢者を「権利の主体者」として捉える人権のお話です。勝手な振る舞いという意味ではなく「やりたいことに向き合う自分の意思は尊重されるべきであること」「社会に貢献したいという思いは受け止められるべきであること」「自分たちのことを決めるときは、自分たちの意見が反映されるべきであること」などです。この「高齢者も『権利の主体者』である」という人権のお話を進めていくうち、明らかに参加者の目が輝き始め、前のめりになってくるのが分かりました。
そこで「皆さんは、日々どのような思いでどのような活動をされていますか?」と問うてみました。次々に手が上がり熱い思いを話されます。「私は今も健康そのもので時々サーフィンをやっています。家族も応援してくれています。」「地域で何かできることをしたいと思い学童の通学見守りボランティアをやっています。子どもたちと触れ合ったり、感謝されたりすることがうれしいです。」「『高齢者支えあいネットワーク会議』に参加し、毎回当事者目線の意見を述べています。」など、出るわ出るわ!いきいきと語る高齢者の思いがさく裂します。
誰もが「権利の主体者」であり、自分の思いや意見を大切に扱ってもらえること、これこそ人間らしく生きるために最も必要な人権の一つであると感じました。
*メルマガ第199号<令和6月28日配信>より


 翻訳
翻訳