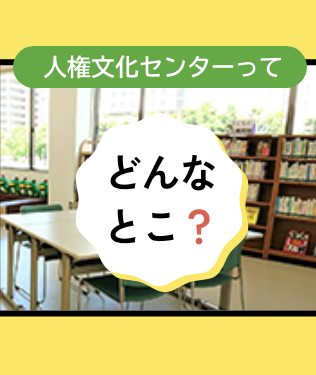じんけん放話5「もう10回目 〇〇甲子園」
夏の甲子園大会は、各試合感動を与えながら慶應義塾高校の優勝で幕を閉じました。残念ながら県勢は早々に姿を消しましたが、鳥取県は9月にも熱く燃える甲子園が開催されます。それは、「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」。平成25年10月、全国で初めて手話を言語と認めた「鳥取県手話言語条例」の制定を機に、翌26年から毎年開催されているこの大会は、皇族の御臨席もあることから毎回マスコミにも広く取り上げられています。
ところで、昨年の優勝は埼玉県の坂戸ろう学園・大宮ろう学園の合同チーム。かつてろう学校で手話の使用が禁止されたという苦難の時代があったこと、そしてそれを乗り越えていく姿を演劇やポエムで紹介しました。実はこの史実は、手話の由来として手話言語条例前文に記載されています。
そして条例本体には、手話を言語として認め手話が使いやすい環境を整備することや、手話を学ぶ機会の確保や学校での手話の普及に努めることなどが規定されています。この10年間の県の取組については、8月19日の日本海新聞の特集記事に今後の展望とともに紹介されています。では、これらの取組により、条例が目的とするろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会が実現するのでしょうか。地域社会の主役は県民です。条例に規定する県民の役割は、「手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたものであること」、そして「手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互の違いを理解し、その個性と人格を互いに尊重することを基本として行われなければならないこと」を理解することです。少し難しい表現になっていますが、手話が今以上に広がっていくためには、特集記事にもあるように、まず手話を知ること、手話に触れることが大事です。
ことしは37都道府県から69チームが申し込み、7月の予選会を突破した15チームが挑む第10回全国手話パフォーマンス甲子園。9月24日とりぎん文化会館梨花ホールでの開催です。また、手話言語条例制定10周年記念ということから、9月16日から24日までの9日間を「とっとり手話フェス」と銘打って様々なイベントも企画されています。
鳥取県手話言語条例
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001784.html
第10回全国高校生手話パフォーマンス甲子園
https://www.pref.tottori.lg.jp/237028.htm
*メルマガ第201号<令和8月23日配信>より


 翻訳
翻訳