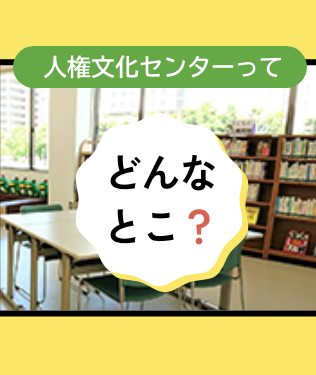じんけん放話6「もやもやする力」
最近、「もやもやする力」が注目されているらしい。これは、イギリスの詩人キーツが1817年に弟に宛てて書いた手紙に登場する「negative capability」という言葉の意訳で、事実や理由はこうだなどと性急に答を出そうとしないで、不確かさや不可解さ、疑惑を抱えつつ、もやもやと考え続ける力のことを言うようだ。意外にも「タイパ」(時間対効果)重視のビジネスの世界で調査研究が進んでおり、医療や介護などさまざまな分野で「もやもやする力」を大切にする取り組みが広がりつつあるというから興味深い。
「もやもやする力」というと、当センターが数年前から実施している対話型人権学習「ふらっとカフェ」を私は連想する。これは、私たちが普段なんとなく分かったつもりでいることを改めて考え、より深く理解しようとする試みであるのだが、ひとつのテーマをじっくり考え、他の参加者と意見を交わしていると、結果的にはスッキリするというより、以前に増してもやもやした状況に陥ることも決して少なくない。ところが、参加者の様子に「さらに分からなくなったじゃないか!」というお怒りはあまり見受けられず、むしろ生じたもやもやをその後も引きずり、考え続けることに価値を見出しておられるようだ。
一方、人権研修の講演においては、今も昔も、分かりやすさは良い研修の重要な指標だ。アンケートに「よく分かりました」と書かれていると、話したことがちゃんと伝わったと思いほっとする。しかし、人権啓発の最終ゴールは講師の話が分かりやすく伝わることではなく、その話を聴いた人が自分を振り返り、社会の見方を深めて、人権擁護に向かう意欲を培うことにある。分かりやすい話を求めすぎると最終ゴールを錯覚するばかりか、分かりやすく単純化されているだけに複雑で多面的な現実には歯が立たないスローガンを繰り返して、講師も参加者も開催者も満足してしまう危険がある。
ところで、当センターには「難しかった」「もやもやした」という感想が続出する講演テーマがある。それは「マジョリティ特権」と「マイクロアグレッション」である。これらのテーマはこれまでの自己理解や社会の見方を転換せよと迫るものであるだけに、もやもや度が高いのもうなづける。
もやもやすることを好む人は少ないだろうが、もやもやのストレスに耐えて考え続けるその先に、自分自身や社会にとって価値ある何かが見つかると期待できる、そんな人権啓発をめざしたい。
(メルマガ第202号<令和9月27日配信>より)


 翻訳
翻訳