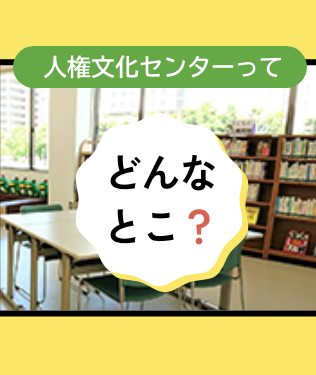じんけん放話22:難しい…でも、考えてみませんか? 特定生殖補助医療について
超党派の議員による「生殖補助医療の在り方を考える議員連盟」は、昨年10月の会合において、第三者からの精子や卵子提供による不妊治療に関し、そのルールを定める「特定生殖補助医療法案」の最終案を示した。
| 生殖補助医療とは 自然妊娠ではなく、医療技術を利用して懐胎し子を出産すること。 ①人工授精 体外に取り出した精子を人工的に子宮に注入する方法。 ・夫の精子による配偶者間人工授精(AIH) ・夫以外の精子による非配偶者間人工授精(AID) ②体外受精 体外で精子と卵子を授精・分割させ、その胚(受精卵)を子宮内に移植する方法。 ・配偶者間体外受精 ・第三者から精子、卵子、胚の提供を受ける非配偶者間体外受精 ③代理懐胎 妻以外の女性に懐胎・出産してもらう方法。 |
日本では、第三者から提供された精子や卵子による不妊治療に関する法律がないまま、70年以上の長きにわたってAIDが行われてきた。公益社団法人日本産科婦人科学会は、2001(平成13)年の厚生労働省の通達※を遵守し、AID以外の提供精子・卵子・胚による生殖補助医療を『必要な制度の整備がなされるまで』実施しないこととしてきたが、中には、独自にガイドラインを作成し、提供精子を用いた体外受精を行うクリニックもある。
最終案では主に次のことが示されている。
- 第三者から提供された精子・卵子・胚を用いた生殖補助医療を、「提供型特定生殖補助医療」と規定。
- 提供者、提供を受けた夫婦、生まれた子どもの情報は、国立成育医療研究センターが100年間保存。
- 成人に達した子が希望すれば、提供者の身長、血液型、年齢等、個人が特定されない情報が開示される。個人の特定につながる情報開示には提供者の同意が必要。
- この医療を実施する医療機関は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 精子や卵子の提供は、内閣総理大臣の許可を得たあっせん機関を通じて行う。あっせんによる利益の授受を禁止。違反への罰則あり。
- 対象者は、「法律婚の夫婦」に限る。
この最終案は、大きく2つの問題が指摘されている。
①生まれた子どもの「出自を知る権利」が保障されているとは言い難い。
親からの告知、あるいは偶然知った等、本医療で生まれた事実を子どもが知ったとき、自分につながる人(提供者)は誰でどんな人なのか、成人に達するまで知ることができず、提供者が拒否すれば個人を特定する情報は得られない(親も提供者の情報開示を求めることができない)。「自分は何者なのか?」という葛藤、遺伝性の病気の有無や体質等を知ることができず、近親婚への不安も生じる。
開示請求できる年齢の引き下げや開示範囲の拡大を求める声もあるが、そうすると提供者が減るのではないかという懸念の声もある。
他にも、親がいつどのように告知するか、公的機関や医療機関がどのように親子をサポートするか等課題は多い。
②妊娠出産を望む事実婚の女性や女性同士のカップル、独身女性が排除されている。
同性カップルや独身女性で、知人やSNSを通じて知り合った男性から精子提供を受け、シリンジを使って自分で体内に注入し、妊娠出産、育児をしている人も少なくない。しかし、提供を受ける際に性被害に遭ったという事例や、感染症に罹る可能性もある等、女性にとってリスクが高い。
最終案では、法律婚以外のカップルについて、法律の公布から5年をめどに見直しを検討するとしているが、切実に子を望む人にとって、5年という歳月がどれほど残酷なものか。この法案が成立すれば、個人間の“取り引き”がさらに増加することが懸念されており、女性、そして母子が危険に晒される可能性が高まる。
議連は、この法案をできるだけ早期に国会に提出したい考えだ。
本医療を望む人、本医療で子を授かった人、本医療で生まれた人、提供者、そして、これから生まれてくる人、それぞれの安心安全が確保され、人権が保障されるためにどうすればよいか。とても難しい問題だが、社会全体で考えていく必要がある。
※厚児母発第1号 平成13年1月17日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長『厚生科学審議会先端医療技術評価部会・生殖補助医療技術に関する専門委員会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」について』


 翻訳
翻訳