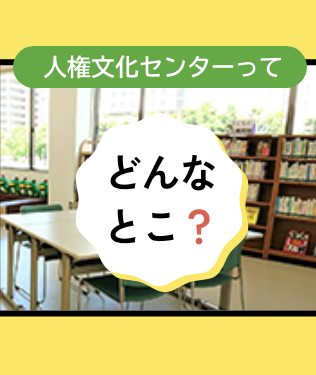じんけん放話25:こども基本法と学校
2023(令和5)年4月、こども家庭庁の設置と同時に「こども基本法」が施行された。3年目になるので、今回は、このこども基本法と学校について考えてみたい。
こども基本法は、こどもの権利全般を包括的に保障する法律であり、国や自治体がこども施策を策定・実施・評価する際、こどもなど当事者の意見を反映するための措置を行うことも求めている(同法第11条)。
そもそも子どもの権利に関する国際的な動きは、約100年前から始まっており、その後、1989(平成1)年に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約」(通称、子どもの権利条約)を日本が批准したのは1994(平成6)年である。その年から29年後に「こども基本法」が施行されたということになる。
こども施策の基本理念(第3条)1号から4号に、「児童の権利に関する条約」の四原則である
「差別の禁止」、
「生命、生存及び発達に対する権利」、
「こどもの意見の尊重」及び
「こどもの最善の利益」を規定し、
5号ではこどもの養育について、6号では子育てを巡る社会環境の整備についての基本理念を定めており、保護者に向けても発信がなされている。
これらの基本理念を学校(教職員)は、どのように受け止めているのだろうか。とても繊細で重要なバランス感覚が必要であると感じる。たとえば、「児童の意見の尊重」(第12条)について、子どもとじっくり向き合い対話を行うことの重要性については多くのみなさんが賛同されると思う。ただ、子どもは「保護の対象者」であると同時に「権利の主体者」でもあるということを、どのように理解し、目の前の子どもにどう働きかけるのかが大切である。
このことについて、「こども基本法」には「その年齢及び発達の程度に応じて」と記されており、一見「なるほど」と思えるが、同じ学年でも全ての子どもの「発達の程度」が全く同じとは考えにくいし、小学校であれば1年生と6年生とでは大きく発達段階が異なる。中学生、高校生の1年生と3年生でも発達段階の違いは明白である。
一般的には子どもの年齢が上がるにつれて、「権利の主体者」として捉えられる場面が多くなっていく。では、学校での様々な決まりや活動について、子どもたちは「権利の主体者」としてどのように関わっているのだろうか。たとえば、校則、制服、授業づくり、運動会の種目、文化祭の内容等、学校の方針と子どもの主体性が、十分な対話による調整によって創造されているかどうか、このことがとても重要である。
「Nothing about us without us」= 「私たちのことを私たち抜きに決めないで」
この言葉は、2006(平成18)年に「障害者権利条約」が国連総会で採択されたときのキーワードであり、日本が「障害者権利条約」を批准したのは、2014(平成26)年である。
令和の時代に沿う学校のあり方、子どもが主体となる学校を創造するためには、まず、子ども自身に自分が「保護の対象者」であると同時に「権利の主体者」でもあるということを理解出来るようにすることが必要である。この理解の深まりについても、「その年齢及び発達の程度に応じて」継続して分かるようにすることが大切である。そして、学校に関わる教職員、保護者も含めて大人もそのことを理解することが重要である。大人の願いは、子どもの成長である。笑顔で、その成長を支える大人でありたい。
※参考 「大人のための10の心得」鳥取県人権文化センター啓発動画


 翻訳
翻訳