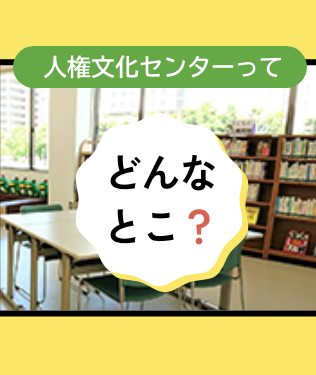じんけん放話26:戦争は最大の人権侵害である
今年は戦後80年、各地で従軍体験や当時の人々の暮らし等を紹介する催し物が開かれています。資料展示や語り部によるお話、映画や演劇、子どもたちへの読み聞かせなど、それぞれの目的に応じて、戦争の悲惨さや平和への思いなどを伝えています。
実際に戦地に赴き戦った兵士たちの記録を読み、原爆投下後の広島長崎の話などを聴くにつけ、現場の惨状には言葉を失います。「何の恨みもない人と人とが殺し合う」とか、「戦争している理由さえ分からない子どもたちまで巻き込まれて殺される」など、到底、人間が行う所業とは思えません。
また、灼熱のジャングルの中で飢餓や病気などが蔓延し、生死の間を彷徨った体験や、抑留者となって過酷な強制労働を強いられた体験などには「人間の尊厳」など無きに等しく、そこに「人権」を考える余地はありません。「戦争は最大の人権侵害である」と言われる所以です。
このような状況を顧みて、戦後、国連においては「世界人権宣言」が、日本では「基本的人権の尊重」、「平和主義」、「国民主権」を軸とした「日本国憲法」が制定されました。これらは、戦争の惨禍を二度と起こさないよう、そして、人間が人間らしく生きていくために必要な「人権」について規定しています。
ある公民館で、戦争を扱った子どもたちへの人権学習に参加しました。戦争の悲惨さばかりを伝えるのではなく、戦争が日常生活に及ぼした影響を考えることで、現代に生きる私たちの暮らしと対比しながら人権の大切さを問うものです。
現憲法においては、例えば、以下のような人権に関する条文が規定されています。「(19条)思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。」、「(21条)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」、「(29条)財産権は、これを侵してはならない。」、「(31条)何人も、法律に定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」などです。現代に生きる私たちからすれば、一見、当たり前と思えるものであり、普段の生活において、これらの条文を改めて問い直すことはほとんどないと思われます。しかし、これらの人権に関する規定が、私たちの暮らしの土台を築いているからこそ、自由で安心できる生活が送れるのです。
「戦時下にあっても平和を訴えることは、19条によって保障されている。しかし、この条文がなかったら・・・」、また、「自分が正しいと思ってやったことが、司法判断を経ることなく、勝手に断罪され刑罰を科せられたとしたら・・・(31条)」などの状況を設定しながら人権の大切さを学んでいく。
「人権は『家族』や『健康』などと同じく、失ってみて初めて、その大切さを実感できるものです。」講師の締めの言葉に子どもたちは、深く頷いていました。


 翻訳
翻訳